PR: あなたの善意が命をつなぐ 骨髄バンク-政府ネットTV
ピータァ・オトゥールについて
ピータァ・オトゥールが亡くなったそうだ。
いつも読んでいる「THE BRADY BLOG」の記事で知った。
XXX
閑話休題。
前述のブログはイギリスのミュージックシーンにまつわる記事を掲載している。
私はイギリスのそれには強い興味はない。
それよりも、筆者の描く「普通のイギリス」が興味深い。
よく知られているようにイギリスにはクラスがある。
日本も格差社会と言われているが、イギリスのクラスはまったく別物である。
旅行者のような立場ではそのクラスを知ることができない。
このブログの筆者は、そこに住み、そこで働き、そこで子育てをしている。
ワーキングクラスの一員として、
ワーキングクラスの人たちの喜怒哀楽を描いている。
マトモな人なら口にしない4文字単語をいちいち語尾に付けて話すような、
そんな人たちの中で暮らしている。
私はリンボウさんのエッセイなども面白く読むが、
あれは異邦人のイギリスであるなぁとつくづく思う。
私が子供の頃に住んでいた地域も、
ヨイトマケ的おっかさんや、ジャージしか服を持ってない同級生などがいたので、
まんざら遠くない気がするのだ。
XXX
ピータァ・オトゥールといえば、
多くの日本人にとっては「アラビアのロレンス」だろうと思う。
私の父親もその映画を大絶賛しており、
そんなに良い映画ならばと、
彼の数少ない蔵書の中にあったその小説を手にしたことがある。
しかし最初の10ページほどで脱落した。
砂漠が暑いの、ラクダに水を飲ませたのと、
(私には)どうでもええ内容がダラダラ続いているだけで、
一向面白くなかったのである。
記憶にある限り、途中で脱落した本はこの1冊だけだ。
みっしりと字の詰まった昔の新潮文庫で読む前に、
映画を見るべきだったのだろう。
動くピータァ・オトゥールを見たのは、
「プランケット城への招待状」である。
「スプラッシュ」の人魚マディソン役のダリル・ハンナが出るというのと、
やっぱりピータァ・オトゥールが見たかったので、
テレビでやっていたのを珍しく見たのだった。
女の子の幽霊と生きている男の子が恋仲になるという話だったと思う。
日本では幽霊と情を交わした人間はあの世に連れて行かれるのが常だが、
欧米のコメディだと、男の子は死なないのだなぁと思った覚えがある。
ピータァについては、思ったほどのスターオーラを出していなかったので、
やはりロレンスを見るべきなのかなぁと思った。
しかし、今になると、キリスト教国によって作られた、
神のみいつの届かない可哀想な国の話を
やはり可哀想な国の住人としては、あまり楽しめる気がしない。
ミスサイゴンも王様と私も蝶々夫人もセブンイヤーズインチベットも、
もっと若いうちに楽しんでおけば良かった。
ちなみにラマンはセンチメンタルの洪水が辛かった(笑)
「ピータァ」という表記はモリマリに依る。
彼女はピータァが大変お好みだったようで、
彼女のエッセイには頻繁に登場する。
彼女のキラキラな単語でキラキラに形容されたピータァは、
私の中では、もはや実際のピータァとは関係なく、
「とにかく無闇な美男」という位置づけだ。
若い頃のピータァはロレンスのスチールで見たきりで、
ガタイの良い面長な彼は、まったく私の好みではなかった。
しかし、私の好みなどどうでもよく、彼は「絶対的な美男」なのだった。
映画なんてあまり興味のない私にも
彼にまつわることがこれだけ書けてしまうのだから、
その点だけでも彼は世界の名優だったのだなぁと思う。
wikipediaによると、彼は長く病床にあったようだ。
どうぞ安らかに。
XXX
なんつーか、スプラッシュなんてのが出てくる時点で、
我ながらアラフォー感満載(笑)
【ゆるぼ】[excel 2010] 数字をフィルターしたい
特定の数字を含むものを選択できなくて困っている。
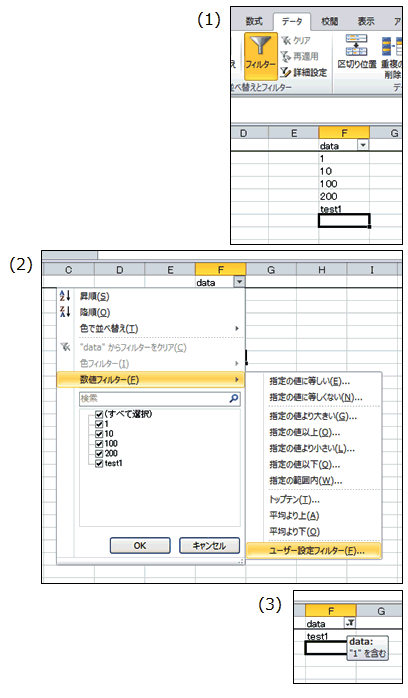
(1)
セルにデータを入力。
セルの表示形式を「文字列」設定する。
フィルタをかける。
(2)
セルを「文字列」に設定したのに、
「数値フィルター」が表示されている。
「ユーザー設定フィルター」を選択して「1を含む」を設定。
(3)
なぜか「test1」しか表示されない。
1, 10, 100 が表示されない。
(2)で検索ボックスに「1」を入力すると、
1, 10, 100, test1 が検索されるけれど、
それはそれで置いておく。
知恵袋などを見ると、
新しい行を挿入し、
数値に何らかの文字をくっつけた文字を入れて、
そちらでフィルターしろと。
例:1 → 1a
実は、アンスコやハイフンが入っていても、フィルターできない。
文字列先頭についていれば、フィルターできる。
例:
1_2_3 → フィルターできない
1-2-3 → フィルターできない
_1 → フィルターできる!
いったいどういう仕様なのこれ。
どうにかならないのかしら。
ウチも10周年
うっかりしてたら、昨日10周年を迎えたぽい。
いろいろあったなぁ(しみじみ
続いてるような、続いてないような、ビミョウな感じだけどねー。
でもま、エキブロやって良かったというのは、確実に言える。
いろんな人とお知り合いになって、
いろんなことを知って、
世界も広がったし。
エキサイトがやってる限り、
だらだらいくかなぁとか。
お葬式っていろいろな件
何が驚いたといって、
いただいたお香典をその場で開けて、
金額を確認して、
金額に見合った引き物をお渡しする、
というシステム。
…開けちゃうんだ、目の前で…。
地域によっていろいろなのね。
独居老人見守りシステムを導入したい件
親の家に見守りシステムの導入が急務。
親は認知症ではない(と思われる)が、
物忘れが激しい。
次の瞬間には忘れている。
さっき言ったよねと説明すると、
「あ、そっか」と思い出す。
(だからたぶん認知症ではない)
でもやっぱり次の瞬間には忘れている。
なわけで、見守りシステム導入が喫緊の課題である。
テレビでも良く取り上げられる見守り電気ポット。
もっとも簡単に見えるが、課題がある。
見慣れないコンセントは抜いてしまいそう。
年寄りは省エネに敏感なのだ。
たぶん「抜かないで」と教えても覚えられない。
セキュリティシステムを導入している上司に聞いたところ、
実質、ぜんぜん役に立っていないのだそうだ。
緊急ボタンをよく押してしまうらしい。
業者が警察を伴って急行して、元気な本人を発見。
でも本人はボタン押したことなど、覚えているわけがない。
ボタンがあったら「これ何かしら?」と押してしまうのは仕方がない。
普段は押しちゃダメと教えても覚えられない。
見守りケータイというのもあるらしい。
しかしケータイは難しいのだ。
持ち歩くだけならできそうだが、
充電しなくてはいけない。
充電器に置く、
毎日充電器から取り上げて携帯する、
こんな難しいこと、年寄りにはまず無理。
充電器に置きっぱなしにするか、
充電しないで電池切れになるか、
充電器のコンセントを抜いてしまうか。
ドアセンサや赤外線人感センサ、マットの圧力センサなどを使った
見守りシステムが良いのかなと思う。
ま、実は最近はそっち方面のプロなんで、
自分でシステム構築できないこともないのだが、
夫に提案したら、
「実証実験レベルのシステムはいらない。
商用サービスレベルの安定性が必要。」と一蹴された。
人命がかかっているわけだから、確かにそうか。
なわけで、悩み中。
Normalization, Standardization, Scaling
使い分けがわからない。
日本語だと「正規化」とか「標準化」とか書いてあって、
あまり厳密に区別していないように見える。
「Normalization Standardization Scaling」で検索すると、
多くの人が混同しているようで、
「違いがわかりません!」というページがたくさん出てくる。
ぜんぶ英語だけど。
で、自分なりにまとめてみた。
間違ってたら教えて偉い人。
・Normalization
各ベクトルのL2ノルムが1になるように収める。
L1ノルムを指定することもあるらしい。
L2ノルムとは各特徴量の二乗の和。
(ノルム norm を使うから normalization なの?)
・Standardization
各ベクトルの平均0、標準偏差1にする。
これは各ベクトルなのか、
全ベクトルの特定の feature ごとなのか、
どっちもアリなのかは不明。
ちなみに R e1071 パッケージ svm の scale オプションは、
TRUE にすると、全ベクトルの各特徴量を串刺しで
ゼロ平均+分散1の変換をするので、
厳密には standardization なのだろうと思う。
(標準偏差を見るから、standardization なのかも)
・Scaling
値を特定の範囲([0,1]とか?[-1,1]とか?)に収める。
これも、各ベクトルなのか、
全ベクトルなのか、
全ベクトルの特定のrowなのか、
全部アリなのかは不明。
normalization も standardization も含めて scaling と言ったり、
別扱いしているページもあったり、
色々でよくわからない。
参考(主なもの):
http://scikit-learn.org/stable/modules/preprocessing.html
http://blog.pengyifan.com/scale-standardize-and-normalize-data/
http://www.faqs.org/faqs/ai-faq/neural-nets/part2/section-16.html
×××
機械学習とかパタン認識とかの説明を読むと、
どうも日本語よりも英語のほうがわかりそうな気がする
(多分に気のせいだと思うんだが)。
日本語に訳して、難しい感じになっちゃったり、
視認性が下がったりして読みづらくなっているのかなぁ。
例えば、クラス分類とクラスタリングを混同する人が多いのも、
classification / clustering と書くと、
全然違うから混同しないのではと思ったり。
Androidアプリをリバースエンジニアリングしてみる
目的
事の発端は、新しくお下がりされた Android 端末である。
標準音楽プレイヤーであるところのWALKMAN様が、私には激しく使いづらい。
前の端末に入っていた標準プレイヤーもイマイチ残念な子だったが、
そっちのほうがまだ良かった。
私が満足できるアプリも(無料では)存在しないようだ。
ならば自分で作るしかない。
しかしちゃんとした Android アプリは作ったことがない。
サンプルだのプロトタイプだのばかりである。
一から作るのは敷居が高い。
そうだ、前の端末の標準プレイヤーの作りを参考にさせてもらおう!
作業環境は windows7。
前の Android 端末はナイショ(使用規約的な意味で)。
準備
参考にしたページは以下。
Androidアプリケーションのリバースエンジニアリング | JUMPERZ.NET Blog
・参考にしたいアプリを前の端末から持ってくる
/system/apk 以下にいた。
少なくとも、*.apk, *.odex のセットが必要。
他に /system/framework も全部PCにコピーしておく。
・リバースエンジニアリング用ツールたちをDL
JDK
smali
baksmali
dex2jar
jad
smali と baksmali は以下から jar を落とす。
Downloads - smali - An assembler/disassembler for Android's dex format - Google Project Hosting
dex2jar は以下。
Downloads - dex2jar - Tools to work with android .dex and java .class files - Google Project Hosting
jad はこちら。
JAD Java Decompiler Download Mirror
apkを解凍
フツウにzip解凍すれば良い。
./myapk/ などをテキトウに作成して配置。
odex → smali
DOS窓で以下を実行。
.\myapk\smali\ 以下に各種ファイルが作成される。
-d の後のは、 /system/framework をコピーしたディレクトリ。
> java -jar baksmali.jar -a 9 -x appli.odex -o .\myapk\smali\ -d .\framework
引数なしで実行するとヘルプが出るので参考にする。
jar や -d の後のディレクトリなどは、ちゃんとパスが解決できるように指定すること。
-a の後の API-Level はこちらで調べた。
AndroidのバージョンとAPIレベルの対応関係
smali ファイルなんか見てもわからないので、作業を続けて *.java にしていく。
smali → dex
dex2jar に掛けるために、いったんdexにする。
.\myapk\smali\ 以下のファイルを dex に変換。
java -jar smali.jar -o .\myapk\appli.dex .\myapk\smali\
dex → jar
.\myapk\appli_dex2jar が作成される。
> dex2jar.sh .\myapk\appli.dex
jar → class
.\myapk\class などを作って、フツウにzip解凍
class → java
.\myapk\class 以下を再帰的にデコンパイルして
*.java というファイル名にして、.\myapk\src ディレクトリに出力。
ディレクトリ構造をそのまま保持してくれるのは嬉しい。
> jad -o -r -sjava -d.\myapk\src .\myapk\class\**\*.class
「Couldn't fully decompile method ...」とか
たくさんのエラーが出るけど、
自分で作るための参考にするだけで、
大まかにわかれば良いので、これでおk。
サンプリング周波数とかビットレートとか
自分の中でごっちゃになっていたので、まとめてみた。
用語
■サンプリングレート
(=サンプリング周波数)
44.1kHz ならば、44100回/秒でデータを取る
波の横幅(細かさ)=音の高さ
サンプリング定理(周波数の2倍でサンプリングすれば元を再現可能)より、
音声周波数22kHzまではサンプリングできる計算になる。
普通のCDは20kHzまでしか録らないのでこれで十分。
ところでサンプリング定理って、
よくわかってないんだけど、
1周期中2点をサンプリングして、
その間を再現するのは正弦波で近似ってまじすか?
■量子化ビット
(=ビット深度)
16ビット ならば、波形の高さを2^16に分割する。
波の高さ=音の大きさ
ビットレートは転送(処理)速度で、単位bps。
量子化ビットとは全然別物。
ちなみに量子化はクオンタイズと言うが、
クオンタイズビットとは言わないらしい。
クオンタイズというと、
DTMらへんでは音のタイミングを合わせる、とかそんな感じ。
ビット深度とビットレート
wikipedia より。
ビットレート = (ビット深度)* (サンプリング周波数)* (チャンネル数)
例えば、サンプリング周波数 44.1kHz、ビット深度 16ビット、2チャンネル(ステレオ)の場合のビットレートは次のようになる:
16 * 44100 * 2 = 1411200 ビット/秒 = 1411.2 kbps
ビットレートとは、単位時間に処理されるデータ量を意味する。
上記の例は CD の場合。
mp3 は、再生機の仕様が最大 320kbps となっていることが多い。
この数字と 1411.2kbps は大分違うように思うが、
この bps は圧縮後のデータ処理速度なので、
CD のビットレートと mp3 のビットレートを比較しても、音質とは無関係。
192kbps の mp3 でも、プロでも wav と聞き分けができないほど
音質は問題ないらしいという話も。
私個人は聞き比べたことがないのでわからない。
録音品質が相当悪くても気にならないタイプだからかも。
身近な仕様
■CD
サンプリング周波数 44.1kHz
音声周波数帯域 20Hz~20kHz
ダイナミックレンジ 96dB(=1ビット6dB * 16bit)
■DVD Audio
サンプリング周波数 48kHz,96kHz,192kHz
音声周波数帯域 ~88kHz(192kHz)
ダイナミックレンジ約146dB(量子化ビット 24bit)
レンジ 96db って、どこを中心にしているのだろう?
というのはおかしいかもしれないが、
0db は音がない状態ではない(私の左耳の聴力は 4kHz で -5db だ)ので、
極端な話 -96db ~ 0db ということもありうるんだよね?
そのあたりは、ミキサーとかプロデューサとかの好みなんだろうか。
あと、レンジが 96db あっても、
イヤホンあたりでは全部再現できないのではないか。
ちゃんとしたウーファーとか要りそう。
今後
ここまで調べて、ロスレスに興味出てきた!
よく見かけるのって、FLAC とか Apple Lossless あたりかな。
とうとうハフマン符号化をちゃんと理解せねばならん時が来たかも(笑
プログラミングできる天才ちょっとこい
ハフマン符号化ってなに?
http://nantara.blog73.fc2.com/blog-entry-461.html
Xperia SO-03D に引越し+思うところ
Android端末、ダンナのお下がりをもらった。
Galaxy S SC-02B(初代)から Xperia SO-03D にお引越しである。
使い始めて3週間。
色々思うところが。
良いところ
・UI が最近の Android ぽい
GalaS はまだ過渡期だったようで、各社バラバラだった。
この3年ほどでキャリアによる味付けの範囲がまとまってきたのだなと思う。
ホームや戻るボタン、設定の仕方などが、かなり最近の Android ぽい。
Xperia は、過剰なカスタマイズがなく、素の Android に近くて使いやすいと思う。
・重みがちょうど良い
GalaS (約120g)よりも重く(約150g)、片手で持つとずっしり感があるが、
その分、片手で操作しているときの安定感が良い。
幅は GalaS と同じくらいで、厚みのほうはちょっと増したものの、
片手での使い勝手はなかなか。
ちょっと残念な気もするところ
・docomo 謹製アプリのプロセス多すぎ
SIM なしで使っているので、これらのプロセスは不要。
root 取ってこれらを kill することもできるが、
不安定になると怖いので、そこまではしないけど、気分的にはしたい。
(/etc/init.d/とかないのかな?)
SIM の有無で起動判定してくれればいいのに。
・システムフォントが少ない
GalaS には「アップルミント」「チョコクッキー」など
ゆるふわ女子力高い系フォントがいくつか入っていた。
お気に入りは「ティンカーベル」で、
アルファベットに邪魔なかわいい星だのピロピロだのが付いていて、
ゆるゆるな脱力感が良かったのだが。
Xperia にも入れたいのだが、どこに入っているのだろう。
GalaS:/system/fonts には見当たらなかった。
追記:/system/app/以下にパッケージとして入っているようだ。
でもフォントの野良パッケージを見つけて入れたので解決。
・プロセス管理しづらい
GalaS には samsung 謹製プロセス管理アプリがあったので、
不要なプロセスをモリモリ切って、電池温存に勤めていたが、それができない。
プロセス管理アプリもあるが、
現在プロセスとして動いている以外の、オンメモリのアプリがわかりづらい。
やや残念なところ
・ホーム画面のショートカット
アプリをインストールすると、自動的にホーム画面にショートカットが作られる。
ホーム画面は基本的にウィジェットのみで、キレイにしておきたい派なので、
いちいち削除しており、非常に面倒くさい。
追記:以下の設定で修正できた
Google Playストア
→ 端末の「MENU」ボタン
→「設定」
→「ショートカットの自動追加」のチェックをはずす
ものすごく残念なところ
標準音楽プレイヤーであるところの天下の SONY ブランド WALKMAN 様が、
私には激しく使いづらい。
ネットの評判を見ると、イコライザとか音質などは良いらしい。
しかし私は生音至上主義なので、そのあたりは重要でない。
・スマートプレイリストが不要
勝手にリストが作られるのは許すとして、
リスト自体を非表示にできない。
リストのナカミも編集できない。
つボイノリオとブラームスと乙女系ドラマが並ぶカオスな状態である。
そして他の音楽プレイヤーを起動すると、
そのプレイリスト一覧もこのリストが出てくる。
不要な場合は、リスト自体を非表示にさせて欲しい。
リストの曲目を削除できるようにして欲しい。
・再生範囲の設定が貧弱
「アーティスト」「アルバム」しかない。
私は聴くジャンルが比較的広めだろうと思うのだが、
それらをフォルダで分けているので、
フォルダごとの再生はマストである。
嘉門達夫も聴くし、ドボルザークも聴くし、アニソンも雅楽も海外の民族音楽も聴く。
「替え歌メドレー」と「新世界」があったら、フォルダ分けたくなるよね?
「フォルダ」は欲しい。
加えて「ジャンル」「年」、可能であれば「作曲者」も加えて欲しい。
・再生範囲の再生順が設定できない
見た目(タイトル順?ファイル名順?)か、シャッフルか、の二択である。
「タイトル順」「ファイル名順」「トラック番号順」などでソートさせて欲しい。
Win7 に BitLocker を入れてみた
OS : Windows 7 Enterprise
CPU : Core i5-4570
BIOS で起動順を変更する必要があるかもしれない。
ハードの詳細やBIOSの設定については
以下の記事を参照。
HP ENVY 700-060jp に Windows7 64bit をインストール
http://xiaoxia.exblog.jp/18756770
ハードが TPM 対応していないので、システムドライブは暗号化できなかった。
TPM 対応していないハードでも、
USBメモリがあればシステムドライブを暗号化できるが、
社内規定でUSBメモリは使えないため、
システムドライブの暗号化は無理ということが判明した。
ドライブ暗号化の要件は以下を参照。
Windows 7 用の BitLocker ドライブ暗号化の手順ガイド
BitLocker ドライブ暗号化の要件
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/dd835565(v=ws.10).aspx#BKMK_require
そこで、システムとデータを別ドライブにして、
データドライブのみ暗号化を行った。
システムドライブを暗号化した場合、
最悪起動しなくなる恐れがあるけれども、それも回避できて、
個人的には一石二鳥。
(参考:ITアーキテクトの「やってはいけない」
- [Windows 7編]ドライブを丸ごと暗号化してはいけない:ITpro
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20100824/351405/ )
TPM 対応していない場合、
よく「ローカル グループ ポリシー エディター」(gpedit.msc)を起動して
設定変更する手順が web に載っているけれど、
データドライブのみ暗号化するのであれば、
この変更は不要ぽい。
暗号化後、1日経ったけど、特に問題なく、
シームレスに使えている。
手順
画面のキャプチャはあちこちに載っているので、
そちらを見てね。
例えばこことか。
【連載】すぐわかるWindows7 第13回 BitLocker<1>|アスキーPC|編集部ブログ
http://asciipc.jp/blog/windows7/windows713bitlocker/
(1)
エクスプローラで、ドライブを選択して右クリックすると
「BitLocker を有効にする」の項目が出るので、
そのまま選択。
(2)
「パスワードを使用してドライブのロックを解除する」にチェック。
パスワードを適宜入力。
(3)
「回復キーをファイルに保存する」を選択。
前述の理由で、USBメモリは使えないし、
印刷だけでは、印刷物をなくしたら終わりなので、ファイル出力。
ファイルの場所を選択。
回復キーファイルを印刷して厳重に保管する。
そのほか、ファイルは
別のマシンにも保存しておく。
とにかく複数の方法であちこちに保存しておく。
(4)
暗号化が開始される。
暗号化にかかった時間は 500GB のドライブで約10時間。
(200GBくらい使用済)
(5)
毎回、再起動後、暗号化したドライブを右クリックしてパスワードを入力。
すごく面倒くさいので、
以下のページを見て、バッチファイルを作成し、
タスクスケジューラで登録して
「最上位の特権で実行する」にチェックを入れると良いぽい。
dsp74118の補完庫: BitLocker/Bitlocker To Goの自動ロック解除についてちょっと研究
http://dsp74118.blogspot.jp/2012/07/bitlockerbitlocker-to-go.html
追記:
バッチファイルをスタートアップに入れるだけでは
管理者ユーザでも管理権限がないので、以下のようなエラーになり、
unlock できない。
BitLocker ドライブ暗号化: 構成ツール Version 6.1.7601
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.
エラー: 必要なリソースにアクセスしようとしましたが拒否されました。
コンピューターの管理権限があることを確認してください。
バッチファイルのショートカットをスタートアップに入れて、
このショートカットを「管理者として実行」しても、
「このコンピュータへの変更を許可しますか」という
UAC ウィンドウがいちいち表示されて面倒くさかった。
というわけで、タスクスケジューラに入れると、
管理権限で実行できて、UAC ウィンドウも出ないで済むぽい。
[Windows7] PC でパケットキャプチャ
今日はパケットキャプチャしてみたよ!
もちろん仕事だよ!
OS : Windows7 64bit
目的
自分の PC に来たパケットをキャプチャして、
スクリプトで編集できる形式(text)のファイルが欲しい。
用意するもの
・Microsoft Message Analyzer
・Wireshark
どっちも無料。
そしてどっちも英語。
だけど、まぁ多分大丈夫。
手順
コマンドプロンプトを管理者権限で開く
メニュー → アクセサリ → コマンドプロンプトのアイコンを右クリック
管理者で開く
パケットをキャプチャ
netsh trace start capture=yes traceFile="C:\file_%date:/=%_%time::=%.etl"
netsh trace stop で終了
以下のような2ファイルが作成される
例) file_20141014_235900.00.etl, file_20141014_235900.00.cab
traceFileオプションを指定しない場合は、
%TEMP%\NetTraces フォルダー内に NetTrace.etl, NetTrace.cab ができる
Microsoft Message Analyzer で変換
Microsoft Message Analyzer で *.etl ファイルを開く
Save As → Export で、*.cap で保存
Wireshark で変換
Wireshark で *.cap を開く
Print → Plain Text
Browse... で出力ファイルを指定して Print
最終結果はこんな感じ。
No. Time Source Destination Protocol Length Info
1 0.000000000 fe80::xxxx:xxxx:xxxx:xxxx ff02::x:x LLMNR 86 Standard query 0xaf28 A isatap
Frame 1: 86 bytes on wire (688 bits), 86 bytes captured (688 bits)
Ethernet II, Src: xxxx-_xx:xx:xx (xx:xx:xx:xx:xx:xx), Dst: IPv6mcast_xx:xx:xx (xx:xx:xx:xx:xx:xx)
Internet Protocol Version 6, Src: xxxx::xxxx:xxxx:xxxx:xxxx (xxxx::xxxx:xxxx:xxxx:xxxx), Dst: ff02::x:x (ff02::x:x)
User Datagram Protocol, Src Port: xx (xx), Dst Port: xx (xx)
Link-local Multicast Name Resolution (query)
No. Time Source Destination Protocol Length Info
2 0.000033600 xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx LLMNR 66 Standard query 0xaf28 A isatap
Frame 2: 66 bytes on wire (528 bits), 66 bytes captured (528 bits)
Ethernet II, Src: Hewlett-_xx:xx:xx (xx:xx:xx:xx:xx:xx), Dst: IPv4mcast_fc (xx:xx:xx:xx:xx:xx)
Internet Protocol Version 4, Src: xxx.xxx.xxx.xxx (xxx.xxx.xxx.xxx), Dst: xxx.xxx.xxx.xxx (xxx.xxx.xxx.xxx)
User Datagram Protocol, Src Port: xx (xx), Dst Port: xx (xx)
Link-local Multicast Name Resolution (query)
...
[ruby]win7 って messagepack-rpc 入る?
今日は ruby の MessagePack を試してみたよ!
これももちろん仕事だよ!
我ながら色々手出してるよね!
そして解決していない内容だから、
あんまり参考にならないと思うよ!
インストール
こんな感じでインストール開始。
gem install msgpack-rpc
通常なら gem install をすると、
Fetching ... というようなメッセージが出るが、
何も表示されない。
そして
突然コードページが変わる
「マシン名#」というプロンプトが出る
という状態になって、そこで停止。
プロンプトが出たので「exit」で抜けてみたら、
mkmf.rb あたりのエラーが。
キャプ取るの忘れたんだけど、確かこんな感じの。
checking for main() -l *** extconf.rb failed ***
gem fetch のみ実行すると正常に実行できて、
gem が落ちてくるので、
gem ファイルを指定して gem install --local をしてみたが、
同じエラーが出て、進まない。
原因がわからない(あんまり追ってない)。
いろんなパッケージを入れてみる
で、とりま Rails と DevKit をインストールしてみた。
再度 msgpack-rpc をインストールしてみる。
> gem install msgpack-rpc
Temporarily enhancing PATH to include DevKit...
ERROR: While executing gem ... (Errno::ENOENT)
No such file or directory @ realpath_rec - D:/Ruby/21-x64/lib/ruby/gems/2.1.0/gems/cool.io-1.1.1
cool.io がないって言われても…。
cool.io を単独でインストールしてみた。
これは成功した。
再再度 msgpack-rpc をインストールしてみる。
…
stat_watcher.c: In function 'Coolio_StatInfo_build':
stat_watcher.c:249:13: error: 'ev_statdata' has no member named 'st_blksize'
stat_watcher.c:250:13: error: 'ev_statdata' has no member named 'st_blocks'
make: *** [stat_watcher.o] Error 1
make failed, exit code 2
ev_statdata ってなにこれ?
まだダメぽい。
ちょっと…かなりイヤになってきた…。
gem list をしてみたら、
messagepack-rcp の依存関係にある rev が入っていない。
gem install rev をする。
成功。
しかし、messagepack-rpc のエラーは変わらず。
openssl-nonblock が必要という話も見たので、
ここのページを見て、 openssl-nonblock も入れてみたが、
このパッケージ自体のインストールに失敗。
rubyのmsgpack-rpcをインストールしようとしたらできなかった - うどん駆動開発
http://d.hatena.ne.jp/r_takaishi/20100914/1284455719
完全に脱落しました(´・ω・`)
もうやだorz
この後、Ubuntu で試したら、さらっと行きました。
ひょっとして Win7(64bit) て、messagepack-rpc が入らない?
[Ubuntu][Ruby] MessagePack-RPC が動かないときに確認
昨日 windows7 ruby に MessagePack-RPC を入れ(ようとして脱落し)た記事を書いたけど、
もうホントに、心底、脱落したわよ(笑
だから Ubuntu に入れることにしちゃった♪
で、とりま動いたので、ここまでで困ったことをメモしておくよ。
動かなかったり、エラーが出た場合の
主に環境を作る段階での確認事項など。
確認すること
実際に実行されるファイル
「ruby」のみで実行した場合
「gems」のみで実行した場合
バージョン
ruby -v で見られるバージョン
gems -v で見られるバージョン
以下のリンク先
/etc/alternatives/ruby
/etc/alternatives/gem
/usr/bin/ruby
/usr/bin/gem
gems の各種情報
gems env で、リポジトリを調べる(httpsだとダメな場合あり)
gems list で、インストールされているパッケージやバージョンを確認
不整合がある場合は、何とかして修正すること。
基本的に apt-get だの gem だので正式に直すのだけど、
リンク先については、手でモリモリ直すものみたい。
ruby1.8, ruby1.9, ruby2.0 など、それぞれのバージョンで
gem の update のやり方などが違うようなので、
ちゃんと確認すること。
特に 1.8 から 1.9 に上がったあたりで、
gem ががっつり変わったぽいよ。
lib の格納場所なんかも変わってるらしいよ。
そのた注意点
・プロクシのある環境
環境変数にプロクシを指定しても、gem が動かない場合がある
gem install などをする際は、-p http://IP:port/ のように指定してみる
・MessagePack のサーバを実行後、EADDRINUSE 系のエラーが出た場合
ポートが使用中で bind できないという意味
使用されていないか調べ、当該ポートを使用しているプロセスをkillする
「netstat -anp」などで表示できる
思いついたらまた追加するわ。
PR: 特別価格で!ルフトハンザの新プレミアムエコノミー
[Windows7] タスクマネージャのグラフの値を取得する
先日、パケットキャプチャしてみたのだが、
実は 一番やりたかったことは、
NIC の I/O の値を取るってことだったの。
sar の rxbyt/s と txbyt/s みたいなのを見たかった。
windows に sar コマンドがあればいいのに。
もしかして、タスクマネージャのネットワークタブで表示される
グラフの数値が取れればいいんじゃないの?ってことで、
その数値を取得するメモ。
特にネットワークの値が欲しかったので、
その内容に特化して書いたけど、
同様のやり方で、CPU 使用率とか、色々取れるよー。
方法
(1)データ収集の設定
パフォーマンス・カウンタの値を収集する。
以下のページを見て、データ取得の設定をする。
パフォーマンス・カウンタのデータをスケジュールに従って収集する(Windows Vista/Windows 7/Windows Server 2008編) - @IT
「記録するパフォーマンスカウンタを選択」の項で、
「Network Interface」 の中の
「Bytes Received/sec」と「Bytes Sent/sec」を選択して「追加>>」。
ICMP とか HTTP とか TCPv6 とか UDP とかあるけど、
sar 相当なら、上記の設定で良いっぽい。
(2)ログを記録、保存
一定時間、実行して記録したら、右クリックなどで「停止」。
(3)出力ファイルを開いて変換
C:/PerfLogs/Admin/データコレクタセット名/マシン名_日付/ファイル名.blg などに出力されるので、
このファイルを開く。
デフォルトはパフォーマンスモニタで開かれる。
どこでも良いので、画面上で右クリック、
「データを保存」を選択して、csv 形式で保存する。
最終結果はこんな感じ。
15秒ごとに取得。
Teredo とか isatap とか必要なのかは良くわかってない。
ウチの LAN て IPv6 使ってたっけ?
"(PDH-CSV 4.0) (","\\MachineName\Network Interface(Teredo Tunneling Pseudo-Interface)\Bytes Received/sec","\\MachineName\Network Interface(isatap.{XXX})\Bytes Received/sec","\\MachineName\Network Interface(isatap.{XXX})\Bytes Received/sec","\\MachineName\Network Interface(Realtek PCIe GBE Family Controller)\Bytes Received/sec","\\MachineName\Network Interface(isatap.{XXX})\Bytes Received/sec","\\MachineName\Network Interface(Teredo Tunneling Pseudo-Interface)\Bytes Sent/sec","\\MachineName\Network Interface(isatap.{XXX})\Bytes Sent/sec","\\MachineName\Network Interface(isatap.{XXX})\Bytes Sent/sec","\\MachineName\Network Interface(Realtek PCIe GBE Family Controller)\Bytes Sent/sec","\\MachineName\Network Interface(isatap.{XXX})\Bytes Sent/sec"
"10/14/2014 23:57:28.195"," "," "," "," "," "," "," "," "," "," "
"10/14/2014 23:57:43.198","0","0","0","774.44912872811244","0","0","0","0","0","0"
"10/14/2014 23:57:58.193","0","0","0","1409.6238705208716","0","0","0","0","10.80324851094622","0"
"10/14/2014 23:58:13.196","0","0","0","798.73811482102087","0","0","0","0","0","0"
"10/14/2014 23:58:28.193","0","0","0","753.44294505548942","0","0","0","0","10.802527400565474","0"
"10/14/2014 23:58:43.197","0","0","0","762.42352784619686","0","0","0","0","0","0"
"10/14/2014 23:58:58.194","0","0","0","1024.1740698628537","0","0","0","0","10.802539183396204","0"
"10/14/2014 23:59:13.199","0","0","0","813.22526171396839","0","0","0","0","0","0"
"10/14/2014 23:59:28.197","0","0","0","675.37976930023842","0","0","0","0","10.801808927499124","0"
atode
iremasu
スキン変えてみた
思い立ってスキン変えてみた![]()
ちょっと前から変えようかなぁと思っていたんだけど、
チューニングするのが面倒で、
そんなら、まぁせっかく用意してくれているのだから、
どれか使ってみるか、みたいな。
女子力あげてみた![]()
性格も変わりそう![]()
ブログのデザインで中の人がどんな人かって考えるの、あるよね![]()
ビミョウに絵文字の使い方が間違ってる感…![]()
(メールで絵文字はほぼつかわないから慣れてない)
[未解決]VirtualBox 起動するとホストでキーボードが使えない
はじめに
タイトル通りの内容です。
ホスト:Windows7 Enterprise
USB機器:
USBハブ+USB変換機(オーテク)+PS2キーボード(IBM SpaceSaver)
ELECOM タッチパッド
いつもは VM は VMWarePlayer を愛用しているのですが、
商用利用ができないので、
展示会でのデモ用に VirtualBox 4.3.26 を入れました。
まだ色々問題も聞きますが、デモのためには仕方がない。
で、既に作成してあった VirtualBox の VM を起動したところ、
ホスト側でキーボードがまったく使えなくなりました。
タッチパッドは使えます。
VirtualBox を終了してもキーボードは使えないので、
仕方なく Windows を再起動しました。
ゲスト側では、キーボードの一部とタッチパッドは使えます。
キーボードに付いている、
ポインティングデバイス(赤い丸とボタン)は使えません。
実施1:VirtualBox の USB 機器に登録→失敗
VirtualBox の設定中にある、USB機器の一覧に
キーボードとタッチパッドを登録しました。
「メーカー」「製品名」「シリアル番号」は空欄にする、と
書いてあるブログを見つけたので、
その通りにしました。
結果は失敗でした。
ホスト側では、
タッチパッドは使えるのですが、
やはりキーボードは使えなくなります。
実施2:Extension Pack を入れる→失敗
USB がらみのトラブルは、Extension Pack を入れるといいよ!という
内容を良く見かけたので、
入れてみました。
状況は変わりません。
まとめ:未解決です
というわけで、誰か助けてー!(笑)
ちなみに、他のマシン(Thinkpad)では
同じ VM が問題なく動作しています。
くやしい。
[SVN]Pristine Text Not Present
SVN を使っていたらこんなエラーメッセージが。
検索して、以下のページを発見。
SVNがらみ - AkiWiki - Pristine Text Not Present
それを治す方法は2つ。
・再チェックアウト
・SmartSVNを使って Validate Admin Area メニューを実行する。
ということなので、
SmartSVN を入れてみた。
ちなみに、
このエラーメッセージが出た原因は不明。
1GB超えの、でかファイル(VMイメージ)が複数あったので、
チェックアウトを中断したりしてたのが原因かも。
(だってDLが終わらないんだもの)
脱線:SVN クライアント
・TortoiseSVN
シェル統合されるのが、ものすごく嫌いだ。
常に SVN を使っているわけではなくて、
必要なときだけ使っているので、
のべつ幕なしに右クリックがべろーんと出るとか、
ちょっと邪魔くさすぎる。
・RapidSVN
ウチの会社のNW環境は、
プロクシだの認証だのがかなり鬱陶しいのだ。
そういう環境を乗り越えるジャンプ力はないみたい。
見た目シンプルで、
SVN のコマンド+アルファくらいの感じは嫌いじゃないだけに残念。
・eclipse
というわけで、現在使っているのはこれ。
エンジニアに憧れているので。
やっぱエンジニアなら IDE で全部済ませるよね!ふは!
Validate Admin Area ってどこ?
SmartSVN を入れてみた。
全部英語だが、SVN 使っている人なら困らない程度の英語である。
ローカルのチェックアウト済みリポジトリを読み込んでみたが、
どこにも Validate Admin Area なんてメニューがない。
と思ったら、どうもコンフリクトしないと表示されないもののようだ。
表示されている画面例をようやく見つけた。
Missing pristine files in SVN working copy | About Git, SVN, and other VCS
オススメの解決法
私の場合は、やっぱり「再チェックアウト」が良いようだ。
というのも、
SmartSVN でいじった後、
eclipse でエラーになって、まったくいじれなくなってしまった。
どうも SmartSVN と eclipse で、
SVNクライアントのバージョンが違ったのが原因のようだ。
……面倒くさい。
そんなこと調べるくらいなら、再チェックアウトするわ。
というわけで、「私の場合は再チェックアウト」と書いたのは
そういう理由である。
今回の現象は SmartSVN が悪いのではなく
複数のクライアントを使う場合は、発生しがちだろうと思う。
というわけで、
複数クライアントを使う場合は、
各クライアントのバージョンに注意
というのが、今回の教訓。

